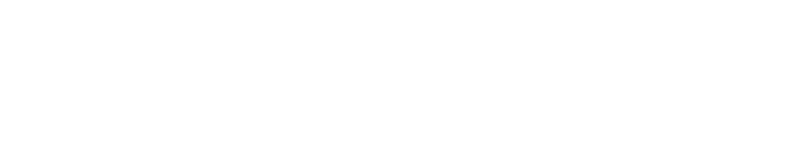ブログ

キャッシュ・フローへの理解・分析
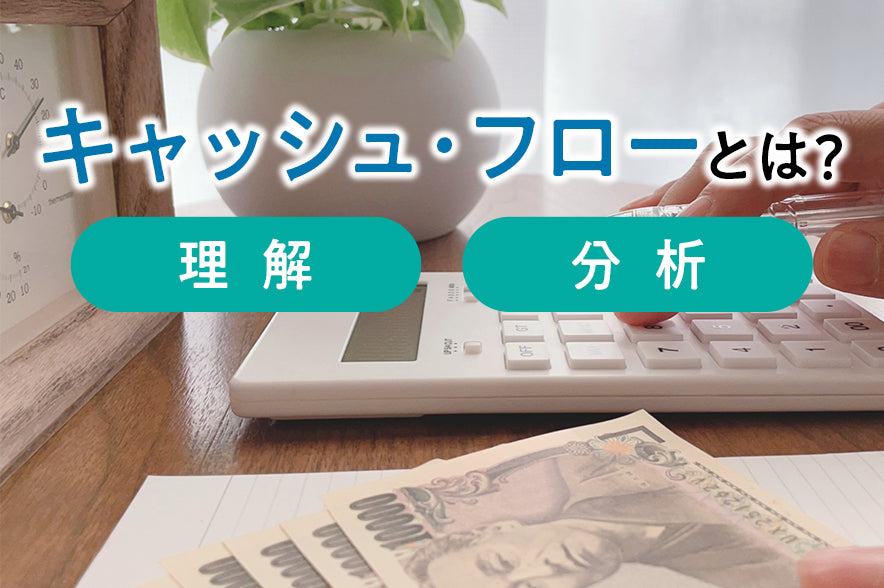
キャッシュ・フローは簡単に言うとお金の流れのことで、企業活動においては重要事項のひとつです。
企業においてキャッシュ・フローはどのような役割を持ち、どのように役立てることができるのか確認してみましょう。
キャッシュ・フローとは
キャッシュ・フローとは、現金流量のことで、現金の流れを意味します。
一定会計期間にどれだけの現金が流入し、どれだけの現金が流出したか、資金の流れを表します。
主に企業活動や財務活動によって実際に得られた収入から、外部への支出を差し引いて手元に残る資金の流れのことをいいます。
また、会社にキャッシュが入ってくることを
キャッシュ・イン、
会社からキャッシュが出ていくことを
キャッシュ・アウト
と言います。
キャッシュとは
キャッシュとは通常、現金のことを指します。
キャッシュ・フローにおけるキャッシュは現金や預金のほかにも、換金性が高くおおよその換金額が分かっている資産も含まれます。
現金は会社の営業活動に必要なものですが、取引上は売掛金や買掛金が生じます。
商品を売り買いした取引は発生しているものの、取引時点で現金の動きはありません。
代金はまとめて月末に振り込みが行われる、といった状態になります。
商品を取引先に売った場合、損益計算書においては「売上」にあがりますが、会社に現金は入っていないというズレが生じます。
例:広告代理店などは1000万円の広告費をgoogleに支払い、広告を出稿し、翌月にクライアントから費用をいただきます。
この時生じたズレがどの程度が把握するための書類をキャッシュ・フロー計算書と言います。
決算書の損益計算書では利益を確認することができますが、実際に企業にある現金を確認するためにはキャッシュ・フロー計算書が必要になります。
キャッシュ・フローと貸借対照表
現金の流れを表す財務三表のひとつに貸借対照表があります。
貸借対照表は、決算日において、現金をどのように工面したか、現金の使い道は何か、会社の財政状態を表します。
工面
株主からの資金のほか、銀行などから借りる、本業によって稼ぐことが工面にあたります。
使い道
使い道とは、何か資産を買った、または預貯金になります。
貸借対照表では、工面した現金と使った現金の数値は最終的に同額となります。
キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書により項目ごとに、どのように流入して、どのように流出したかを表します。
貸借対照表は、最終的に現金の増減の辻褄が合うので会社の財政を確認できますが、現金の流れが健全であるか確認する際にキャッシュ・フロー計算書と照らし合わせます。
損益計算書
財務三表にはもう一つ、損益計算書があります。
損益計算書は、一定会計期間の会社の経営成績を表します。
売上高に対し、どれほどの費用がかかったか差し引くことで、現在の損益がわかります。
これは「当期純利益」や「粗利」と呼ぶこともあります。
損益計算書では売掛金や買掛金の取引を含め、会社の経営成績を表しますが、キャッシュ・フローは取引上の損益を反映せず、現金の流れのみを表します。
キャッシュ・フローの種類
キャッシュ・フローでは現金の流れをタイプ別に分類します。
営業キャッシュ・フロー

日常的な生産・営業活動によって獲得する現金と、それに要する現金コストの収支を表します。
本業に関わる現金であれば、税の支払いのように他のキャッシュ・フローに区分されないものも含まれます。
東京証券取引所ジャスダック市場では、5期連続で営業キャッシュ・フローが赤字の上場企業は、上場廃止基準によって上場廃止となります。
投資キャッシュ・フロー
工場新設やビル建設・トラック購入などといった設備投資、有価証券投資に要する現金支払いと資産売却による収入を指します。
財務キャッシュ・フロー
財務活動による現金の収支を指します。資金の調達や借金の返済といった現金の増減を表します。
株式発行による収入、配当金の支払いなども財務キャッシュ・フローに含まれます。
キャッシュ・フロー分析
キャッシュ・フロー分析は、特定の期間における企業のキャッシュ・フローを分析するものです。
特定期間の期初における現金と期末における現金の差異を見ますが、流出現金よりも流入現金が大きいのが理想です。
キャッシュ・フロー分析は、財務部門によって実施される健全性チェックであり、全ての支出が責任をもって行われることや現金漏出の発見、フリーキャッシュ(自由に使えるキャッシュ)が実際にフリーであることを確保するために実施されます。
フリーキャッシュ・フロー
フリーキャッシュは文字通り
「自由に使えるキャッシュ」
という意味です。
企業活動を通じて得た資金のうち、自由に使える現金を意味します。
計算方法
フリーキャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローと投資キャッシュ・フローの合計で算出できます。
フリーキャッシュ・フローのプラスが大きければ、手元資金を厚くできる可能性が高く安定した企業ということになります。
事業活動における目標の一つは「フリーキャッシュ・フローの最大化」と言われることもあります。事業活動分析において基本となる指標です。
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書、現金流量表は企業会計について報告する財務諸表のひとつです。
会計期間における資金の増減を営業活動、投資活動、財務活動ごとに区分して表示します。
企業会計において、損益は必ずしも現金等の収支と一致しません。
損益計算書上は多額の利益があっても現金が不足すれば企業は黒字倒産に追い込まれてしまいます。
例えば、金融機関からの借り入れは現金の増加、つまり収入となりますが、損益計算における収益ではありません。
また、減価償却費は損益計算上費用となりますが、同一会計期間における現金支出とは一致しません。
キャッシュ・フロー計算書の作成目的は、損益計算書とは別の観点から企業の資金状況を開示することにあります。
具体的には、企業の現金創出能力と支払い能力を査定するのに役立つ情報を提供すること、および利益の質を評価するのに役立つ情報を提供することにあるとされています。
アメリカ合衆国やイギリス等の欧米諸国では1980年代後半から1990年代初頭にかけてその作成が制度化されています。
日本においても国際会計基準の一元化の流れの1つとして「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」の導入に伴い、上場企業では2000年3月期から作成が義務づけられました。
21世紀初頭現在では、主要な先進国の企業会計制度において、貸借対照表と損益計算書に次ぐ第3の財務諸表として位置付けられています。
キャッシュ・フロー計算書に対する評価
債券評価で確立したDCF法等の金融工学の成果を企業評価や事業評価に応用しようとする機関投資家等は、企業や事業の評価を会計上の利益から現金創出力、特に「フリー・キャッシュ・フロー(FCF)」)に重きを置くようになり、その前提として、キャッシュ・フロー計算書の作成を求めるようになりました。
ただし、近年はさらに研究が進み、企業価値評価にFCFの直接的な使用が適当であるかの評価は定まっていません。
また、キャッシュ・フロー計算書は企業の財務状態において、以下の点を評価するのに役立ちます。
・企業が将来の資金流入を生み出す能力があるか
・企業が債務や配当金を支払う能力があるか
・利益やそれに伴う現金の受け取りや支払いの違いの理由
・企業の投資と財務の取引の現金及び現金以外の側面
資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書において、資金とは現金および現金同等物をいいます。
現金・キャッシュとは、手許現金および普通預金や当座預金などの要求払預金を指し、現金同等物とは、容易に換金可能かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資を指します。
具体的には、定期預金(3ヶ月以内のもの)、譲渡性預金、コマーシャル・ペーパーなどがこれに含まれます。現金と現金同等物間での取引はキャッシュ・フロー計算書には表示されません。
直接法・間接法
キャッシュ・フロー計算書を作成する方法には、直接法と間接法があります。
・直接法
直接法は現金収支に収益・費用を関連付けて計算します。
直接法は間接法に比べてキャッシュ・フローに対する収益・費用の関連性を表記できる反面、実務が煩雑である難点を持っています。
直接法の連結キャッシュ・フロー計算書を作成するためには、通常、連結側に取り込まれない「売上原価」の内訳を連結側に取り込み、内訳毎の連結消去が必要となります。
しかし、この機能を実現している連結会計システムはごく一部に限定されています。
IFRS(International Financial Reporting Standards:国際財務報告基準)は直接法に一本化される方向であり、米国基準も直接法を推奨しています。
・間接法
間接法は利益から非資金性費用を加算して資産・負債の増加減少を逆算する事により計算する方法です。
つまり間接法によるキャッシュ・フロー計算書では、損益計算書の税引前当期純利益を元にキャッシュ・フロー要因の期首との差異を加減することで計算します。
実務では間接法によることが多くなっています。
これは、特に連結での直接法キャッシュ・フロー計算書が作成困難であり、比較的に間接法によって作成することが簡便であることが理由の一つです。
また、中国の「新企業会計準則」では2012年1月1日より、間接法は禁止されています。
表示区分
キャッシュ・フロー計算書の表示区分は以下の3つです。
・営業活動
直接法、または間接法により作成することが選択でき、どちらの方法で作成しても結果は同じ金額となります。
企業活動との関係性を明らかにするため、支払利息の支払額は「財務活動」に、受取利息や受取配当金の受取額は「投資活動」にそれぞれ記載することも出来ます。
したがって、「小計」欄が純粋な営業活動によるキャッシュ・フローです。
・投資活動
直接法により作成します。営業活動以外での資産に関わる全ての資金の動きを示します。
主に固定資産の取得や資金の貸付による資金の増減、他社への資本投資に関して記載します。
・財務活動
直接法により作成します。営業活動以外での負債と純資産の部に関わる全ての資金の動きを示します。
主に借入金による調達や返済の増減や、自社の株や債権に関する発行益・配当金支払・買戻・返済などを記載します。
意義と分析
キャッシュ・フロー計算書は、企業活動における様々な情報を提供します。
それらの内容を分析することで、企業活動に関して以下のようなことが明確になります。
・キャッシュを生み出す現金創出力
・資本の活用方針
・借入金に係る支払利息の負担能力
・外部からの資金調達への依存度
・収益力の質と量
キャッシュ・フロー評価
キャッシュ・フロー評価は、経済学および会計学において、キャッシュ・フローをもとにした企業やプロジェクトに対する価値評価方法です。
キャッシュ・フロー評価の手法には、いくつかの方法があります。
正味現在価値法
正味現在価値は、将来に受け取れる価値が、もし現在受け取れるとした場合にどの程度の価値を持つか表すものです。
将来のネット・キャッシュ・フローを資本コストで割り引き、そこから投資額を差し引いた価値で評価を行います。
内部収益率法

内部収益率は、投資によって得られると見込まれる利回りのことです。
将来のキャッシュ・フローの現在価値と投資額が同じになる割引率を求めます。
回収期間法
何年で最初の投資が回収されるかで評価を行います。
平均回収率法
投資期間中の平均的なキャッシュ・フローを平均的な投資額で割ったもので評価を行います。
まとめ
いかがだったでしょうか。
世の中ではキャッシュフロー計算書とも呼ばれ、資金繰りの明確化を行っています。
キャッシュ・フローを理解し、キャッシュ・フロー計算書を読めるようになれば、自由に使える資金がいくらあるのかを把握するための手助けにできます。
企業の業績を把握する場合、最も重要視されるのは利益です。
しかし利益を上げるためには資金が必要不可欠です。
資金を管理できるようになれば、利益をあげるためにリスクを抑えた経営が可能になります。
株式会社バランスネットワークは熊本を元気にしていくため、キャッシュ・フロー経営に特化した活動を行っています。
会社の目的を明確にし、キャッシュ・フロー利益を確保するための計画立案から実行までのチーム構築と運用サポートを行います。
経営者や財務・経理のことが苦手という方にも多くの事例をもとに、おススメのキャッシュ・フロー経営講座も行っています。